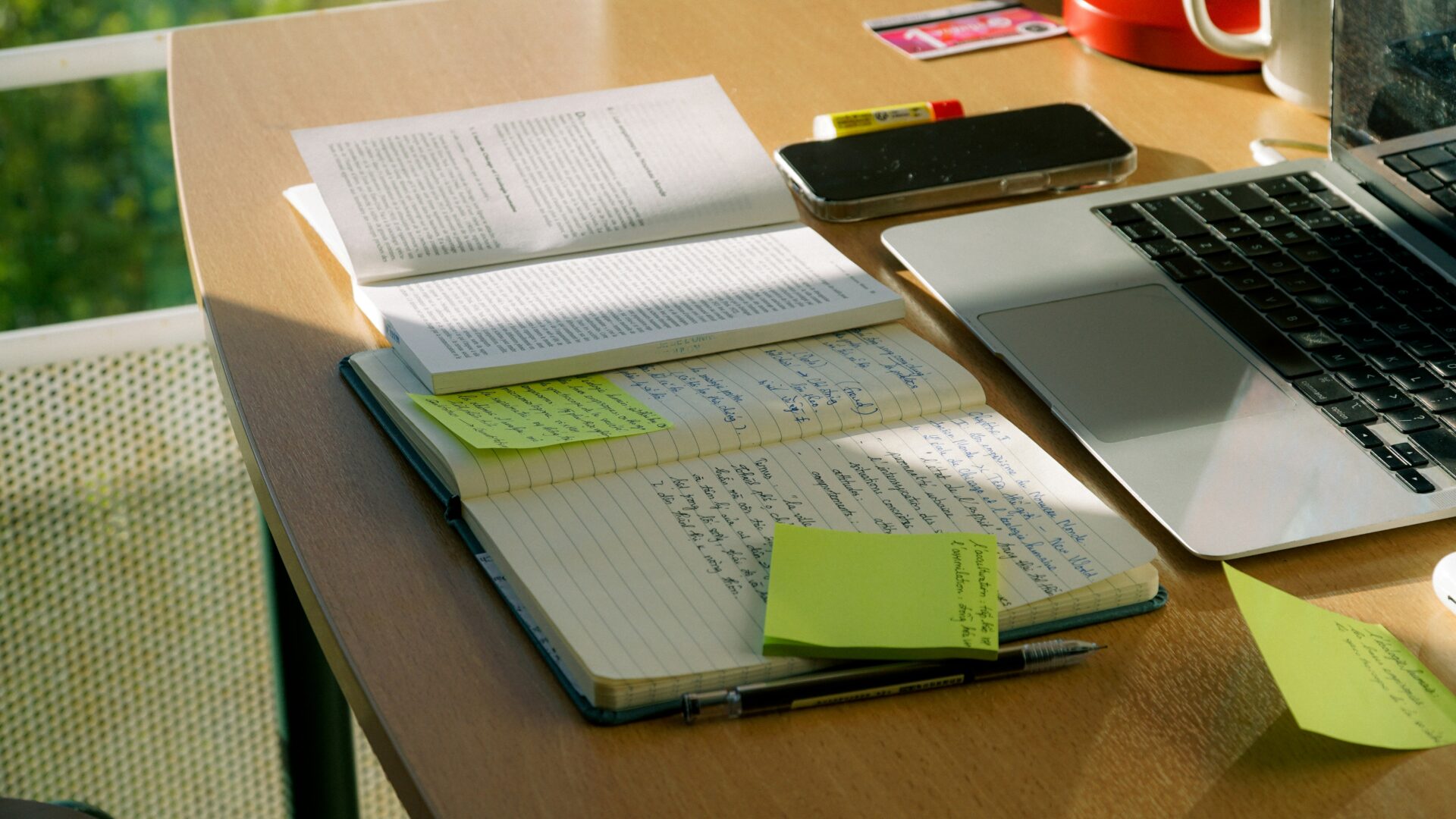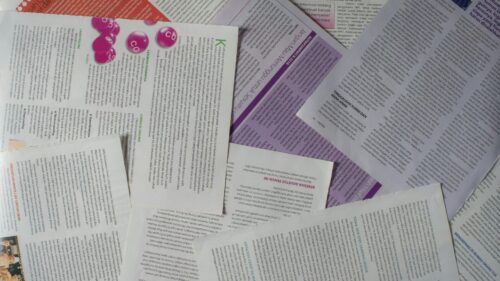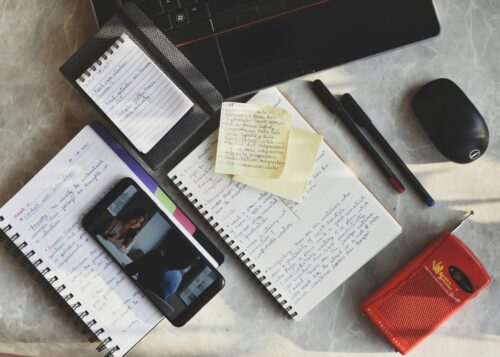こんにちは、シロックマです!
研究の世界では、同じ論文を読んでも人によって見えるものが違います。
学部時代は「書かれていること」を理解するだけで精一杯でも、経験を重ねると「書かれていないこと」や「歴史的な背景」まで、研究者の視界はどう広がっていくのか。
アメリカで化学研究を行う夫・太巻きさんに、論文読解の進化を4つの段階に分けて語ってもらいました。
第1段階:書いてあることが理解できる

初心者がまず目指すべきゴール
研究を始めたばかりの学生は、論文を読んでも意味が分からないことがほとんど。
最初のステップは、論文の構成(Introduction、Discussionなど)を理解し、正確に要約できることです。
この段階では、「論文の読み方」に沿って基礎を固めることが重要です。
第2段階:書かれていないことが見える

批評・レビューが可能になるレベル
背景知識や実験経験が増えてくると、「この実験は行われていないのでは?」といった研究の穴や不足点が見えるようになります。
この段階から、論文に対する建設的な批評やレビューが可能になります。
太巻きさんの学び方
・未知の論文を1ヶ月かけて1本徹底的に読み込む
・引用文献も含め、背景や手法を完全に理解
・まるで自分がその実験を行ったかのように説明できる状態まで掘り下げる
こうした訓練を繰り返すことで、自分の研究分野における「やられていないこと」が見えるようになります。
第3段階:他分野への応用が見える

視野が一気に広がる瞬間
自分の専門分野だけでなく、関連分野の研究にも応用可能な技術やアイディアを見つけられる段階です。
学会や他分野の発表でも、その研究の可能性や不足点が理解でき、共同研究のきっかけにもなります。
第4段階:歴史的文脈や研究リスクが見える
研究を俯瞰できる視点
ここまで来ると、その研究が科学史の中でどの位置にあるのか、またどのようなリスクを背負って成果を得たのかまで見えるようになります。
例えば、新しい技術の登場によって可能になった研究なのか、長期間の挑戦の末に得られた成果なのかが判断できます。
実験系の構築や時間的リスクまで見抜けるようになれば、その論文の価値をより深く評価できます。
おまけ:抄読会の意義

太巻きさんは、「抄読会は発表者のための訓練の場」と考えています。
徹底的に読み込み、どんな質問にも答えられるようにすることで理解が深まります。
一方で、聞くだけの立場では得られるものが少なく、主体的な学びが大切だと語ります。
まとめ
太巻きさんが語った論文読解の4段階は以下の通りです。
- 自分の分野で書いてあることが読める
- 自分の分野で書かれていないことが見える
- 他分野でも書かれていないことが見える
- 歴史的背景や研究リスクまで見える
論文読解は、経験と努力によって視界が広がっていくプロセスです。
もしこの先に「まだ見えていない世界」があるなら、興味があるので、ぜひ教えてください。
🎧 詳しくはPodcastでお聴きいただけます